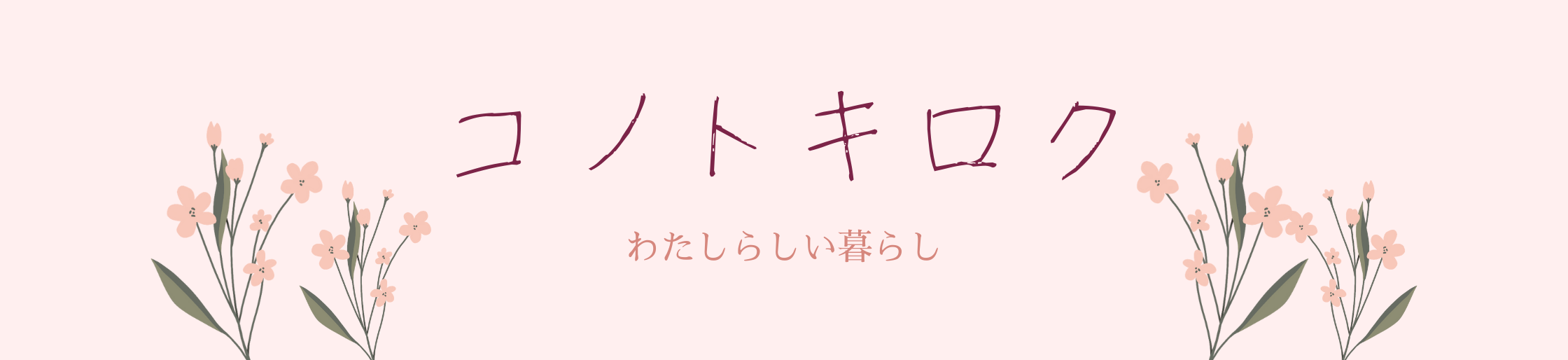こんにちは~rikoです。
夫の6月給与明細とともに住民税決定通知書が届きました!
さて、ふるさと納税はちゃんと反映されているでしょうか!?確認します。
- 住民税決定通知書を確認したい理由
- ふるさと納税の控除は、どういう流れで反映される??
- ふるさと納税の控除額は、どこで見る??
- その他の確認したいところ
- 我が家が利用しているのは「楽天ふるさと納税」
- さいごに
住民税決定通知書を確認したい理由
じつは私、5年間、人事部での勤務経験があります。
給与計算、それに伴う各種税金の処理
給与計算はもちろん毎月なのですが、季節ごとに行う処理も多い!
例えば、住民税や社会保険料の更新、年末調整などですね。
住民税の場合、自治体からの通知を人事部にて入力などを行い、給与計算に反映させています。従業員数によるかと思いますが、作業量が多く大変…
給与計算をやっていた側から思うと、どんな処理にも間違いがないとは言い切れない…というわけです。(ふるさと納税の控除は勤務先で行うものではありませんが…)
そこで配付される「住民税決定通知書」です。
「ふるさと納税」やその他控除など自分の目で確認しましょう!
万が一、ワンストップ納税の申請書を出し忘れていた…なんて、うっかりにも気づくことができます。その場合、確定申告をすることで還付を受けることができます。(過去5年間)
ふるさと納税の控除は、どういう流れで反映される??
そもそも住民税は前年の収入に応じて決まります。 では居住地の自治体が個人の前年の収入をどのように把握しているかというと①か②になります。
①企業などに勤めている方:勤務先より居住地の自治体へ年末調整した結果を通知
②個人事業主の方や確定申告が必要な方:所轄税務署での確定申告結果が居住地の自治体へ通知
今回は、我が家も当てはまる①の場合についてみてみます。
①の場合、ふるさと納税の控除を受けるには「確定申告」を行うか、期日までに「ワンストップ特例制度」の申請書を寄付先に提出しておく必要があります。(手続きの詳細は省略します。)
その後、どういう風に情報が通知されていくかというと・・・簡単に図を書いてみました!

つまり居住地の自治体では、勤務先と所轄税務署、ふるさと納税の寄付先である自治体と複数からの情報が集まって、それを元に住民税が計算されるわけです。
そんなこんなで計算された住民税額が勤務先へ通知され、それを勤務先が給与システムへ反映させるのです!
ちなみに人事部の処理としては、一定の住民がいる自治体の場合、データで貰える場合もあり、その時は取込み後、確認作業を行います。
ただ社員の住む地域も色々です。自治体によっては、データで無いこともあり、人事部で手入力が必要でした。(働いていたのが前のことで状況が違うかもしれませんが…)
長く書いていますが、 つまり!
住民税が更新され、給与計算されるまでの道のりは長い~笑
複数の機関や処理を経ているので、元人事部としても、ぜひ確認していただきたい!です。
ふるさと納税の控除額は、どこで見る??
<ふるさと納税の控除額>
我が家の居住地の自治体では、このように記載がありました。
摘要欄
寄付金税額控除額○○円※1は税額控除に含みます。
内)申告特例控除額は◇◇円※2です。
〇〇円※1
ここが寄付額合計ー自己負担2,000円になっていれば、「ワンストップ特例制度」 の申請がきちんと反映されていることになります。
(ちなみに端数の関係か、我が家は自己負担1,998円でした!)
ここが合っていれば、まず問題はありません。
◇◇円※2
申告特例控除とは、ワンストップ納税の場合の特例分のことです。
本来の制度上、所得税から控除される分(確定申告時)ですが、ワンストップ特例制度を利用したため、住民税より控除されます。
ただこちらは※1に含まれているので、あまり気にしなくても良いと思います。
摘要欄の○○円※1がどこの数字に含まれるかというと、税額欄の市、県の税額控除額のところになります。ただし税額控除額にはその他の税額控除も含まれるため、そのものの数字にはなりません。
我が家の場合ですが、
税額控除額(市+県)=住宅ローン税額控除+調整控除+寄付金控除〇〇円※1
のようになっていました。
すべて住民税の制度をすべて理解するのは難しいです!
「住民税決定通知書」の裏面に住民税計算方法等が細かく記載されていますが、なかなか読むだけでも大変…笑
(摘要)だけでも確認すると良いですね。
その他の確認したいところ
もう少し詳しく見たい場合は、追加で確認すると良いと思うところを書いてみます。
(専門家ではないので、参考程度に)
<住民税決定通知書>
・配偶者控除、扶養親族区分などが合ってる?
・各種、所得控除がされている?
・住宅借入金等特別控除の税額控除額がある?
住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税で控除しきれなかった場合、住民税でも引かれます。その場合、摘要欄に記載があります。
これらは、源泉徴収票と見比べてみると良いですね。
所得税と住民税では計算が違うので、控除額はあわないことがありますが、その項目に数字やチェックが入っているか?を見ると良いと思います!
またこちらも確認します。
<給与明細>
住民税決定通知書は自治体より発行されていますが、給与処理するのは、勤務先ですので、給与明細とも照らし合わせると良いです。
・住民税の決定通知書の納付額と給与明細で引かれている金額は合ってる?
住民税は税額を12ヶ月に等分して給与から引かれます。ただし端数は6月分で調整しますので、6月のみ金額が違うことが多いです!
勤務先のシステムによりますが、6月、7月が正しい金額で給与明細に載っていれば、おそらく問題ないかと思います~
我が家が利用しているのは「楽天ふるさと納税」
お買い物マラソン時にあわせて行い、ポイントUPを狙ってます♪
今まで行った「ふるさと納税」は、お米や食品ばかりですね。
食費が助かります!
ここ2年は、お米の定期便で半年分を頼んでいます♪
いくつもの自治体が行っていますよ~
定期的に宅配されるので、重いお米をお店で買わなくていいのが便利!
そして、美味しいです!
さいごに
私の拙い説明ですが、住民税決定通知書の確認ポイントについて簡単にまとめてみました!税金関係の計算は複雑だし、言葉も難しいし、よくわからないことが多いです。
ただ、せっかく行った「ふるさと納税」が反映されていなかったら…なんて、もったいない!
ちょっとだけ気を向けて、確認したいですね。
少しでも参考になれば嬉しいです!
ではでは。